日本語が昔から持っていた色の言葉

「あれは何色?」と言われたら、多くの人は「赤だね」とか「緑だよ」などと答えると思います。
歴史的に見てみると、現在のようにたくさんの色の名前を日本語が持つようになったのは、さほど古くないそうです。
昔は、どのように色の名前を使っていたのでしょうか。
ここでは、「日本語が昔から持っていた色の言葉」についてみていきたいと思います。
「〇〇い」が使える色の名前は4つしかない
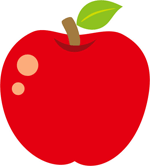
皆さんがリンゴを説明するときには「赤いリンゴ」とか「青いリンゴ」などと言うと思います。
色の名前は単体でも使いますし、形容詞(~いで終わる言葉)としても使います。
では、「緑」はどうでしょうか。「緑い葉っぱ」とは言わないですよね。
いやいや「黄」の場合には、「きいろい」と言うよ、というかもしれませんが、漢字で書くと「黄色い」で「色」という別の言葉が入っていることが分かります。
「黄いレモン」とは言いませんね。
同じように「茶色い」とは言いますが、「茶い」とは言いません。
他の色の名前でも試してみると、色の名前単体でそこに「い」を付けられる言葉は実は4つしかありません。
「赤」、「青」、「黒」、「白」です。
この4つの色名には後ろにそのまま「い」を付けても自然に使えます。
このことから、日本語で昔から使っていた色は「赤、青、黒、白」の4つだったのではないかと推測されるそうです。
でもこれだけだと少し証拠が足りないでしょうか。
では、別の角度からも見てみましょう。
対になる表現があるのもこの4つだけ
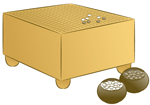
対になる表現とは、例えば「紅白歌合戦」の時の「紅白」(赤白)のようなもののことです。
- 「赤」と「白」(紅白、赤白帽子など)
- 「赤」と「青」(赤鬼、青鬼など)
- 「黒」と「白」(囲碁などは白黒ですし、悪いことをしたときに「シロ・クロ」とも言います)
このような、反対の色を持つ言葉は、この4つ以外に日本語では存在しません。
さらに、「色の名前を重ねた副詞」があるのも、この4つの色だけです。
副詞とは「名詞以外について、それをより詳しく説明する言葉」です。
例えば、「すぐに」などです。
「彼は来た」だけだと、いつ来たのか分かりませんが、「彼はすぐに来た」だと早く来たことが分かりますね。
ここでは、「来た」という動詞を「すぐに」という副詞がより詳しく説明しているのです。
本題に戻って色名を重ねた副詞についてみてみましょう。
この4つの色名を重ねた副詞とは、
- 「赤々と」
- 「青々と」
- 「白々と」(しらじらと)
- 「黒々と」
というものです。

「緑々」という言葉はありませんし、「黄々」というような言葉もありません。
このように、この4つの色は単純に色を表すだけではなく、様々な使い方がなされていました。
したがって、この4つの色がそれだけ長い歴史を持ち、当時の人々がこの4つの色名を巧みに操って自分の考えを伝えていたと考えることができる、というわけです。
では、昔の人はこの4つの色をどのように使っていたのでしょうか。
4つの色の使い方
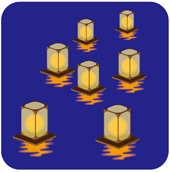
今の私たちの使う日本語では、「赤」、「青」、「黒」、「白」だけでは示す範囲が狭すぎて、うまく相手にイメージや状態を伝えられません。
しかし、昔はこの4つしかなくても会話が成立していたと仮定すると、これらの色はもっと広い意味で使われていたのかもしれません。
このことについては研究が進んでいて、文字を使いだす前の日本語では、特定の色を示す言葉はなく、「明るさ」と「濃さ」だけで色を判別していたらしいということが分かっています。
具体的には、
- 明るい・・・赤(あかは「明るい」に由来)
- 暗い・・・黒(くろは「暗い」に由来)
- 濃い・・・白(しろは「しろし(著し)」(はっきりしているという意味)に由来)
- 薄い・・・青(あおは「淡い」に由来)
だったと考えられているそうです。
つまり、明るいなあと思えばすべて「赤い」と言っていて、暗いなあと思えば全部「黒い」と言っていたわけです。
「白」と「青」も同じです。
この通りだったとすると、今の私たちの感覚とはずいぶん違いますね。
有名な清少納言の「枕草子」の冒頭、「春はあけぼの、やうやうしろくなりゆく、山ぎは・・・」の「しろくなりゆく」は、色として白く光ると同時に、朝日に照らされて風景の色が濃くなってきた、という意味でも使っていたと考えられます。
続きの、「少しあかりて・・・」の「あかりて」も、「赤くなってきた」と「明るくなってきた」をかけた意味と捉えると、情景が非常にリアルに思い浮かびますね。
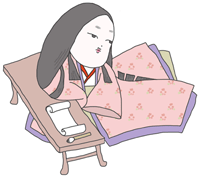
実は、清少納言がこれを書いていた時期(平安時代)には、今のような色の名前で色を示すというやり方がすでに使われだしていた(枕草子でも「紫だちたる雲」などが出てきますね)ので、こんな「掛け言葉のような使い方」が出来たのだそうです。
※古墳時代から飛鳥時代にかけて色名が登場し始め、その後平安時代に貴族の服装の自由度が増して、様々な色が出てきたことに伴って色名も増えたようです。
ただし、少なくとも平安時代には色名とその元になった言葉が、まだ完全には分離していなかったようです。
4つの色は世界を豊かにしてきた
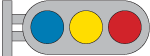
さて、昔から日本語にある「赤」「青」「黒」「白」という4つの色は日本語に基盤を置き、長い歴史を持つことから、様々な派生的な意味を持っています。
「真っ赤な太陽」と言いますが、太陽を見ても赤くはないですね。
むしろ白く見えます。
でもこれは「赤」が「明るい」という意味を持つことを考えると、不自然には聞こえないでしょう。
「青りんご」も、実際は緑です。
しかし青は「淡い」という意味から「未成熟」あるいは「若い」、「新鮮」といった意味が派生しているので「まだ熟していないりんご」だと理解できます。
ちなみに、緑色を青で表す言葉が日本語にはたくさんあります。
「腹黒い」もおなかを見ても実際に黒いわけではありませんが、黒が「暗い」という意味を持つことから、意地が悪いとか陰険、悪いことという意味を伴っているのでいまだに使われます。
新しい言葉でも、ブラック企業などでこの考え方が使われていますね。
同様に「白ける」は、もとは「白」のはっきりさせるという意味から「本当のことを言う」といった意味でしたが、さらにそれが転じて「素になってしまう」「本来の感情のない自分が出てきてしまう」というような意味になっています。
このように、この4つの色は、単に色の名前を指すのではなく、そこから派生して様々な心情や状況の表し方を私たちに与えてくれています。
信号などで「なんで緑なのに青信号なんだ」という人がいますが、あれは日本語の歴史の中で育ってきた表現方法の一つです。



